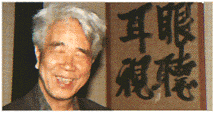
1993年、それは「青い窓」の姉妹誌が十誌に達することを約束された年であります。
そこで、まず姉妹誌の概略をご紹介致しましょう。
誌名、発行地、発行年月の順に記します。
「青い窓」 郡山市 昭和33年5月
「サイロ」 帯広市 昭和35年1月
「金沢青い窓」 金沢市 昭和41年6月
「ひばり」 水戸市 昭和49年3月
「豊っ子」 大分市 昭和61年8月
「青銀詩の窓」 青森市 平成3年5月
「おきなわ青い窓」 那覇市 平成3年11月
「大阪青い窓」 大阪市 平成4年7月
そしてさらに今年は佐世保市と横浜市に開設される予定です。
このように「青い窓」の姉妹誌は北海道から沖縄まで文字通り日本列島に添って、
その土地でなければ生まれてこない児童詩をそれぞれの土地で育んでおります。
そのような作品を数篇ご紹介しましょう。
夕やけ
小学四年
佐々木 昌代
知らぬまに夕焼けが
家の中に入って来た
ノックもせずに
れいぎしらずだ
夕焼けは
だまって入って来たことを
はずかしいのか
顔をまっかにしている
私は
知らぬまに夕焼けを
ゆるしていた
(北海道帯広市の小学校)
ゆうやけ雲
小学五年
工藤 ひなゑ
まっかな まっかなゆうやけ
空いちめんに
ひろがったゆうやけ
そのゆうやけ雲の上に
くろいくろい雲が多く
まっかなきれいな雲が消えてゆく
もうすぐ夜だな
きっとこのゆうやけは私のように
今日は元気にあそんだ
とても楽しかった
明日もまたね
お休みなさい
と今日一日のおわかれに
おもいっきりきれいな雲になって
私たちに話しかけている
(福島県いわき市の小学校)
夕やけ
小学五年
飯森 こず恵
まっかにそまった空
顔も体もみんな
オレンジ色
目の中が
オレンジ色に
もえている
きれいだなあ
明日もまた
あそびたいな
(沖縄県那覇市の小学校)
この三篇は特に地域性という観点から選び出したものではありません。
点訳されて手許にあった作品の中から同じ題のものを抜き出したに過ぎないのです。
しかしそれにもかかわらず私には、はっきりと地域性が見えて来るのです。
たとえば、帯広の作品からは「家」、いわきの作品からは「町」、
そして沖縄の作品からは「空」といったイメージが読後の私の心の中にくっきりと
残るのです。
それはまぎれもなく作品の背景となっている風土そのものなのでしょう。
禅に「随所に主となれば、立所みな真なり」(臨済録)という言葉があります。
つまり、自分自身の主人公が自分であれば、どこにいようと、その立っている所が
全て真実である、というほどの意味になりましょう。
地域に根ざす児童詩とは、とりもなおさずこの禅語の具現にほかなりません。
だからこそイーハトーブの宮沢賢治と同じく、児童詩にもまた、中央や地方はなく、
詩を生んだその土地、その人が主体なのです。
いいかえれば、空間的、社会的位置が問題なのではなく、その主体性が問題なのです。
「随所に主となる」、この言葉を今年はしっかりかみしめていきたいと思います。
(平成五年 青い窓一月号に掲載)
**********************************************************
姉妹誌では、詩集や句集の発行、詩のパネルの掲示などさまざまな形で
活動が展開されました。
平成五年以降、ロサンゼルス「青い窓U.S.A.」、宇都宮市「青ぶどう」、
白河市「白河・青い窓」が創刊されています。
しかし現在では、本文中で紹介した団体も含め、活動を終了した姉妹誌も
多く、継続していくことの難しさを感じます。
それぞれの姉妹誌には忘れがたい作品があり、子どもの詩心を大切に育まれた
方々との素晴らしい出会いがありました。
随所に主となり生まれた作品は、今もなお幸せな記憶として心に刻まれています。
(解説・青い窓の会事務局)
